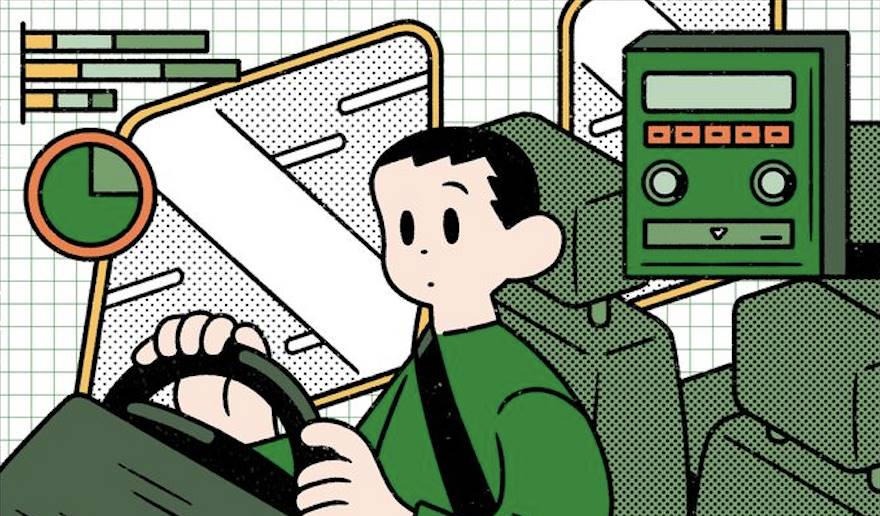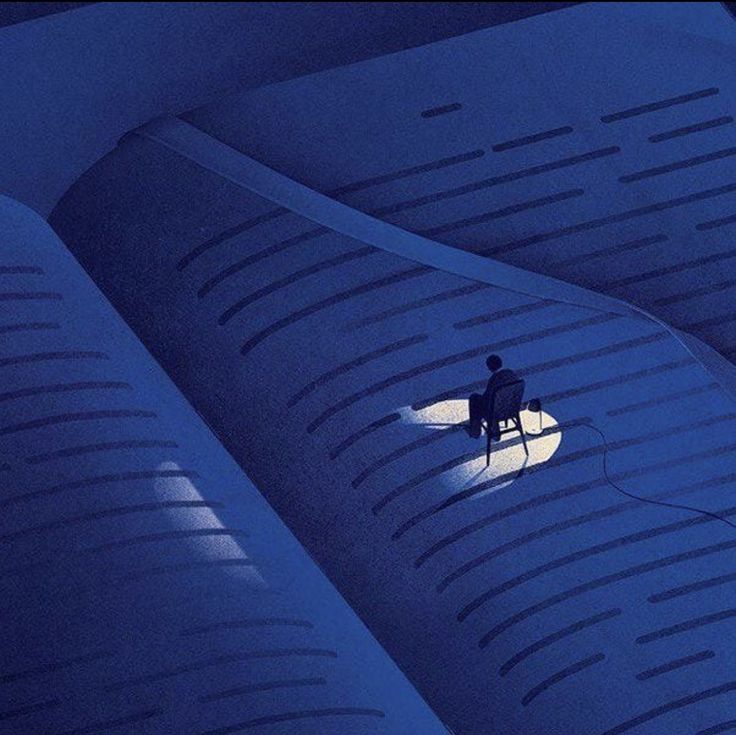事件に関係する仮想通貨は現金化する必要があるか?
TechFlow厳選深潮セレクト

事件に関係する仮想通貨は現金化する必要があるか?
仮想通貨の刑事事件における換価処分に法的論争があり、実務上の規範が急務。
執筆:劉正要弁護士
刑事事件において、現在ネット犯罪はほぼ半数を占めるまでに至っている。そしてそのネット犯罪の中でも、仮想通貨関連の刑事事件の件数はますます増加しており、他を押しのけてトップの座に上り詰めつつある。
仮想通貨関連の刑事事件について、実務面でも理論面でも議論となる問題がある。それは、「捜査対象となった仮想通貨を現金化すべきか否か」というものだ。この問題にはすでに前提が含まれており、すなわち「仮想通貨は財産的価値を持つ」という点である(ただし主流の仮想通貨に限る)。しかし現在でも、一部の司法関係者はすべての仮想通貨はコンピュータ情報システムのデータにすぎないと考える者がおり、このような見解は明らかに現実および法理に反している。したがって、以下の議論はすべて「主流の仮想通貨は財産的価値を持つ」という前提に基づいて行う。
この問題に対する答えは、案件の性質や処理の必要性によって異なる。
一、仮想通貨が証拠として扱われる場合
刑事事件において、証拠となる物品が財産的価値を持っていても、それが法定通貨(有形・無形を問わず)の形で存在しない場合には、原則として現金化処分は行われない。
窃盗罪を例にとると、AがBのビットコイン1枚を盗んだ場合、裁判所がAの窃盗罪成立を認定するのには何ら法的障壁はない。もし当該ビットコインが押収されたとしても、司法機関がそれを被害者Bに返還すればよいだけである。また、Aの犯罪額を確定する場合であっても、そのビットコインを実際に現金化する必要はない。実務上は通常、Bがビットコインを購入した時点での金額をAの窃盗額とする(「被害者の不利益補償」の原則から、司法機関はビットコインの価格上昇部分を考慮すべきではない。詳細は『押収された仮想通貨が保管中に価値が上昇または下落した場合どうするか』参照)。また、Bのビットコインが他人からの贈与または自らの採掘によって得られたものであれば、窃盗行為発生時の市場価格に基づいて犯罪額を算定することが可能である。
こうした手続きではいずれも、ビットコインを実際に現金化する必要はない。なぜなら、問題のビットコインは最終的に被害者(B)に返還される運びだからである。

二、仮想通貨が違法所得とみなされる場合
いくつかの事件では、押収された仮想通貨を被害者に返還する必要がない(たとえば容疑者が既に売却済み、あるいは被害者のいない刑事事件など)場合、通常は仮想通貨を現金化することを検討する必要がある。
中国の刑事司法において、仮想通貨関連事件の多くは経済・金融犯罪であり、これらの事件には原則として罰金刑が科される。罰金の額は、容疑者/被告人の違法所得と密接に関連しているため、結果として違法所得の額を確定するために、仮想通貨を現金化する必要が生じる。
さらに重要な理由として、仮想通貨が違法所得である場合、その価格が事件の立件基準を満たすかどうかを決定づけることがある。仮想通貨の価格は時期によって大きく変動するため、被害者が通報した時点で価格が高く立件基準を満たしていても、公安・検察・裁判所の三段階を経た後に価格がゼロになる可能性もある。このような場合、容疑者/被告人が受ける刑罰がどれほど軽くても、内心では納得できないだろう――「価値がゼロの仮想通貨によって自分を犯罪者と認定するとは一体どういうことか」と。そのため、仮想通貨が違法所得とされる場合は、速やかな現金化が求められるのである。
もちろん、現実は複雑である。ある刑事事件において、仮想通貨が証拠でありながら同時に違法所得でもあるというケースもある。このような場合、司法機関としては証拠の固定が完了した後、優先的に現金化を検討すべきである(ただしUSDTやUSDCなどのステーブルコインについては、当面の間、現金化せずともよいかもしれない)。
また、事件がすでに裁判所の判決を受けているかどうかも、重要な判断要素となる。
三、裁判所の判決前の仮想通貨の処分
我が国では原則として、裁判所が判決を下した後に初めて涉案財物の処分が行われる。したがって、特に事情がない限り、仮想通貨についても判決後に司法処分を行うべきである。しかし、原則があれば例外もつきものである。
『公安機関による刑事事件処理手続規定』(以下「『手続規定』」)によれば、市場価格の変動が大きい株式、債券、投資信託口座などについて、当事者本人の申請または同意があり、かつ県級公安機関の主要責任者の承認を得た場合、判決前であっても合法的に競売・売却が可能である。これに関しては主に二つの議論がある。
第一に、「仮想通貨」は『手続規定』に列挙された「株式、債券、投資信託口座など」に該当するのか。条文中の「など」を拡大解釈できるかどうかは明確ではない。
第二に、『手続規定』はあくまで公安機関の単独の規程であり、刑事事件は公安・検察・裁判所の三機関が協力し、相互に監督しあう仕組みになっている。部門規章的性格を持つ『手続規定』の効力は当然、検察や裁判所には及ばない。したがって、『手続規定』が仮想通貨の先行的司法処分の根拠として、公安・検察・裁判所の三機関を統一できるのかという問題がある。
前述の第一の議論について、司法機関にとって「法に権限を与えられていないことはしてはならない」というのは基本原則である。もし『手続規定』に「仮想通貨」が明記されていなければ、公安機関が勝手に処分することはできないように思える。ただし、ここでの争点は、「など」の語をどのように解釈するかであり、仮想通貨を含める拡大解釈が可能かどうかについては、立場によって異なる見解があり、現時点では統一された見解は存在しない。
第二の議論について言えば、確かに法律や司法解釈の効力は部門規章よりも上位にあるが、残念ながら現状では涉案財物の処分について法律または司法解釈が明確に規定しているわけではない。最高人民法院が制定した『刑事訴訟法解釈』では、事件に付随して移送された涉案財物、または裁判所が差押えた財物については、第一審判決が確定した後に処理するとされている。しかし、公安機関が仮想通貨を事件に付随して移送しなかった場合はどうなるか? この場合、『刑事訴訟法解釈』の規定も適用できなくなる。(この点に関する詳細分析は『仮想通貨の処分はどの段階で行うべきか? 公安か、裁判所か』参照)
以上の分析により、現時点で仮想通貨の処分方法が統一されていない実情が理解できる。解決策としては、関連部門規章や司法解釈のさらなる明文化・細分化が求められ、とりわけ仮想通貨を将来的な立法・司法手続に明確に取り入れていく必要がある。

四、裁判所の判決後の仮想通貨の処分
裁判所の判決後に仮想通貨を処分することは最も「正統」な方法であり、一般的に以下の二通りのケースが見られる。
一つ目は、司法機関が押収した仮想通貨が主流のステーブルコインである場合。ステーブルコインは価格が安定しているため、刑事立案から裁判所判決までほとんど価値変動がない。このような場合、判決後に処分を行うことは道理にかなっている(ただし、仮想通貨を被害者に返還する必要がある場合は除く)。
二つ目は、仮想通貨の価値が下落していない前提で、司法機関が価格鑑定/評価を行った場合。この場合、実質的には仮想通貨が現金化されていなくても、形式的には仮想通貨の価格について一定の公的な資料が提出され、裁判所も鑑定機関・価格評価機関・司法会計機関の意見をそのまま採用することが多い。ただし、Web3.0時代の刑事弁護士として劉弁護士は指摘する。現行の法律・規制および仮想通貨に対する監督方針によれば、中国ではいかなる組織・機関も仮想通貨取引の価格付けサービスを提供することを許可されていない。したがって、前述の第三者機関が仮想通貨の価格を認定することには、法的根拠がまったく存在しないのである。
結論として、仮想通貨を現金化するかどうか、またいつ処分すべきかという点について、現時点の司法実務には統一がなく、その根本原因は、仮想通貨に対する法制度・政策監督の曖昧な態度にある。つまり、仮想通貨の金融的属性を認めたくない一方で、その実際の価値を無視できないジレンマが存在するのである。ある意味で、仮想通貨は権力を握る者たちに対し、草の根レベルの一般大衆が投げかける問いかけといえるかもしれない。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ:https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント:https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント:https://x.com/BlockFlow_News